子供に読解力をつけさせるにはどうしたらいいの?
そんな悩みをもつ方は多いと思います。
私もそんな悩める親の一人。
この記事では、読解力とはなにか?どうやって身につけていけばいいか?我が家が実際に取り組んだことを書いています。
読解力は一朝一夕に身につくものではありませんが、ポイントを押さえて本を読んでいけば身についていくものだと思います。
この記事が読解力を身につけるヒントになれば幸いです。
読解力はどうやって身につける?佐藤ママ流読解力の育て方
私も悩める親の一人と先ほど書きましたが、なぜ悩んでいるかというと小5の娘が読解力がなくて苦戦しているからなんです。
読解力に悩むのはやはり中学受験や高校受験に直面した時ではないでしょうか。
そんな悩める親である私は、なんとかして娘に読解力をつけさせたいと思い、佐藤亮子さんの「我が家はこうして読解力をつけました」という本を読みました。
佐藤亮子さんといえば、三男一女を東大理科三類に入れたスーパーママです。
佐藤ママがいうには、
読解力とは「2Dの文章を頭の中で3D映像に立ち上げてイメージできる能力」
だそうです。
では読解力を育てるために佐藤ママはどんなことをしたのでしょう?
「3歳までに絵本を1万冊、童謡を1万曲」をクリアしたというのです。
佐藤ママが選んだのは「くもんすいせん図書」です。
「くもんすいせん図書」を一気に200冊、そのあと100冊を追加で買ったそうです。
同じ本を何回読んでもカウントされますので、佐藤ママは長男にせがまれて同じ本を最高54回も読んだことがあるそうです。
また、「読解力を育てるには6歳までの幼児教育が大切」だそうです。佐藤ママは子供4人をそれぞれ1歳頃から公文に通わせ、国語と算数を学ばせています。
小さいころから言葉のシャワーを浴びせ、文字や数字に親しませてきました。
つまり幼児教育がとても大事と佐藤ママは言います。

じゃあ6歳までに読み聞かせをしていない子は、もう手遅れってこと?
-3-1.png)
-3-1.png)
-3-1.png)
手遅れという事はないと思います。
佐藤ママはつまり沢山の本を子供に読み聞かせしたわけです。
絵本は絵と文がセットになって目や耳から入ってきますから、語彙力が増え、想像力が豊かになり、集中力が付き、会話も上手になります。
同じ本を何回も読むという行為もまた良いと思うんです。図書館で借りてきて1回読んだだけの本ってやっぱり忘れてしまうんですよね。
小さいうちに読み聞かせを沢山することが望ましいですが、出来なかったからと言って、手遅れという事はありません。
小さい頃に読めなかったら今読めばいいのです。
本を読みたがらないお子さんは、本の内容に興味がなかったり、難しすぎたりするのだと思います。
その子の興味のある分野を選んでみたり、すこし易しめの本から始めてみると良いと思います。
本嫌いの子にも本好きな子にもおススメなのは絵本100冊チャレンジです。
絵本100冊チャレンジ
我が家は小1と小5の娘と一緒に絵本100冊チャレンジをしました。
100冊チャレンジやるよ~と子供たちに宣言すると子供たちもすっかりやる気になって、一緒に図書館で本を借りてきて毎日読みました。
本嫌いの子でも、絵本だったらスラスラ読めると思いますし、100冊読もう!と明確な目標があれば、大人も子供も頑張れるものです。絵本だったら1日かるく10冊くらいは読めてしまいますし、後述する「くもんすいせん図書」は良書がそろっているので、内容的にも申し分なく、なにより「100冊読んだ」という達成感が、子供に大きな自信をあたえます。
うちの長女も本嫌いだとは思っていましたが、結構読めていて、親が思っているほど本嫌いではないことが分かりました。
本人も「私、こういう本好きだな。」と自分が好きなジャンルも分かってきたようでした。
絵本の選び方



100冊読むと言ってもどんな本を選べばいいのかしら?
そんな方には、「くもんすいせん図書」がとてもおススメです。
くもんすいせん図書
絵本100冊チャレンジをするにあたり、我が家はくもんすいせん図書を図書館で借りてきました。
くもんすいせん図書の一覧をプリントアウトしてきて、読んだ本にマーカーを塗りながら100冊達成を目指します。




まず学年相当のところから読んでみて少し読みずらいな‥と思ったら、すこしランクを下げて読みやすいところから読み始めると良いと思います。


絵本定期便の活用
子供が小さくて、図書館にいったり選んだりする暇がないという方には、絵本定期便を活用してみるというのもおすすめです。
①童話館ぶっくくらぶ
長男が小さい頃は童話館ぶっくくらぶの絵本定期便を頼んでいました。
毎月子供の年齢にあわせて2冊届けてくれるサービスで、これがとても良かったんです。
自分じゃ選ばないような本が届いてそれがきっかけでその作者の本が好きになったり、何度も読むのでその物語にも愛着がわいたり・・子供が小さい時って、図書館にいくのも大変だったりしますからこのサービスはとても助かりました。
②ワールドライブラリーパーソナル
ワールドライブラリーパーソナルは世界の絵本の定期便です。
30ヵ国を超える国と地域から選び抜かれた絵本を日本語翻訳し毎月お届け。
様々な国と地域の、文化、色彩、考え方にふれて国際的な感覚を養えます。
しかけ絵本や飛び出す絵本も届きます。
2021年4月から22年3月の間ギフトラッピングを希望したお客様はバースデーカードが届くそうです。


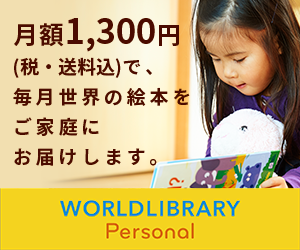
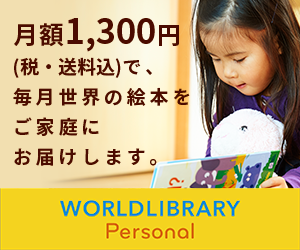
絵本を読むことで身につけられること
絵本や本を読むと身につけられることはたくさんあります。
これらは全て読解力の柱となるものです。
(絵本や本を沢山読むことで身につけられること)
- 文章を読むことに慣れる
- 語彙力があがる
- 知識が増える
- 集中力がつく
- 想像力が養われる
- 本を好きになるきっかけになる
本が嫌いという子でも、絵本を読んでいるうちに本の楽しさを知り、本への興味・関心、読書へのきっかけになることもあります。
私が住んでいる地域では図書館で一人20冊まで借りられるので、インターネットで予約しておいて届いたら取りに行きます。
3歳くらいまでだと親が読まないといけないですが、二人とも小学生なので、一人でどんどん読んでくれるのも忙しい私には助かっています。私も別の機会に一人で読んで、「この本おもしろかったね」などと言い合っています。
だるまちゃんシリーズは気に入って全部のシリーズを借りてきました。
子供が難しいと感じて読まない本は読んであげたり、一度図書館に返して、もう少し読書に慣れてから改めてチャレンジしてみるのでもいいと思います。


絵本や児童書を100冊子供たちと一緒に読んでみて
(追記)2021年12月10日から始めて2021年12月末に次女が、2022年1月初めに長女が100冊読み終わりました。
100冊読んでみて、知らなかった沢山の名作と出会うことが出来ました。
特にレオ・レオニ氏の絵本は、スイミーしか知らなかったのですが絵も内容も大人が読んでも素晴らしいと思える作品で感動しました。
子供達も色んな名作を楽しんでいましたよ。
ただ、100冊読んだからと言ってすぐに読解力が身につくかと言われたらそういう事でもありません。
あくまでも100冊チャレンジは本を好きになったり、本に対する抵抗を無くすきっかけにすぎません。
我が家も100冊チャレンジをやったのをきっかけに本を読む習慣を身につけることが出来ました。
是非「絵本100冊チャレンジ」をやってみてください。
まとめ
今回の記事ではこのようなことを解説してみました。
- 読解力とは「2Dの文章を頭の中で3D映像に立ち上げてイメージできる能力」
- 読解力を高めるためには沢山の本を読むことが大事。
- 本は「くもん推薦図書」がおすすめ
- まずは絵本を100冊読んで、本を読む習慣を身につけよう
- 自分にちょうどいいレベルから読んでみよう
学ぶことに遅いことはありません。
読解力は今後ますます人間に求められる能力だと言われています。
最近の受験の傾向を見ても、「思考力」「判断力」「表現力」などを問う問題が増えてきています。
受験だけではなく、本を読むことで沢山の言葉を覚えたり視野も広がるので、自分の気持ちを的確に現わせるようになったり、思考を深める土台にもなります。つまり生きる力になります。
ぜひ読書を通じて読解力そして生きる力を身につけて欲しいと思います。





















コメント